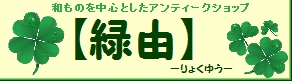ブログランキングにご協力お願いしまーす。
↓クリックして下さるとカウントされてランキングが上がります。。
![]()
今日は久々にアンティークのお話です。。
萬古焼(ばんこやき)についてお話しようと思います。。
昭和53年に国の伝統的工芸品に指定されました。

萬古焼(ばんこやき)は、三重県四日市でつくられています。
代表的なのは、土鍋で全国のシェアの8割を占めるのだとか。
確かに
親戚や知り合いの家にあった土鍋も萬古焼(ばんこやき)でした。。
それと同じくらい有名なのが、紫泥急須(しでいきゅうす)です。

紫泥(しでい)とはよく言ったもので、
まさしく紫色の泥のよう。
 これは、焼くときに「還元焼成(かんげんしょうせい)」といって、酸素を極力送り込まずに焼く方法で仕上げてあるためです。
これは、焼くときに「還元焼成(かんげんしょうせい)」といって、酸素を極力送り込まずに焼く方法で仕上げてあるためです。
模様は、カンナなどで削ってつけます。
 使えば使うほど味わいが出て光沢も増すといわれています。。
使えば使うほど味わいが出て光沢も増すといわれています。。
さて、この萬古焼(ばんこやき)は、煎茶器のセットです。
せっかくですので、煎茶器のご説明もしましょうか。。
まず、急須(きゅうす)。
 これは、だれでもなじみのある茶器ですよね。
これは、だれでもなじみのある茶器ですよね。
ちなみに、急須にも形の種類があって
これは取っ手が横についているため「横手(よこて)」と言います。

次に、湯冷(ゆざまし)。
 安いお茶葉ほどカンカンに沸いたお湯で入れるといいといいますが、
安いお茶葉ほどカンカンに沸いたお湯で入れるといいといいますが、
煎茶道で使う上質なお茶葉(例えば玉露など)は、
少しぬるめのお湯を使います。
そのためお湯を冷ますのに使うのが、この湯冷(ゆざまし)なのです。
口が大きく、注ぎ口があります。

そして、何より大切なのが茶碗です。
 口縁部が少し反っている形をしています。これを端反(はたぞり)といいます。。
口縁部が少し反っている形をしています。これを端反(はたぞり)といいます。。
この茶碗は、内側に白の釉薬がかけられていて趣があります。

きっと緑茶の淡い緑が美しく感じられることでしょう。。

煎茶道は、茶道よりも馴染(なじ)みがなく、難しいかもしれません。
でも、美味しいお茶を美味しい方法でいただくという視点から見ると
そんなに難しいものでもないかもしれませんね
【緑由】、煎茶道についてもまだまだ勉強が必要です。。