ブログランキングにご協力お願いしまーす。
↓クリックして下さるとカウントされてランキングが上がります。。

↓ネットショップ【緑由】にアクセスします♪
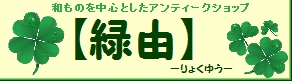
昨日に引き続き、
日本刀(にほんとう)の帽子(ぼうし)のお話をします。。
ついにカテゴリーに
「日本刀なお仕事。」を
作っちゃいました。。
日本刀についてのお話は
このカテゴリーで読んで下さいませ。。
日本刀には、
それぞれの部分に名称があります。。
鎬(しのぎ)を削る
鍔(つば)競(ぜ)り合い
恋の鞘(さや)当て
なんて言葉を聞いたことがありませんか?
みーんな刀の部分の名称が入っています。。
鎬(しのぎ)、鍔(つば)、鞘(さや)。
日本人がいかに
日本刀と深く関わってきたかがわかるような。。。
さてさて、
昨日話題にした帽子(ぼうし)。
今日は写真を用意しました!
御協力は、
㈶日本美術刀剣保存協会 香川県支部が発行した
『讃州鍛冶(さんしゅうかじ)』という本です。
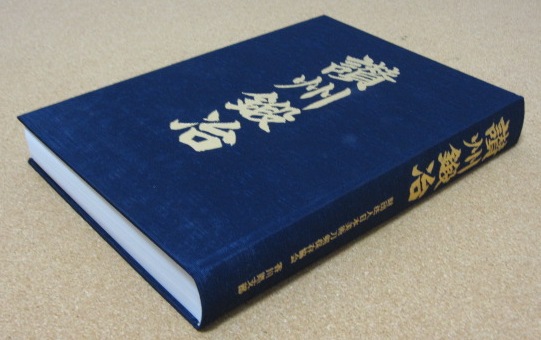 香川県の日本刀を網羅(もうら)した
香川県の日本刀を網羅(もうら)した
とってもスゴイ本。。
この中の写真を使わせていただきました。。
本来の刀の姿を使って
画像処理して赤線を引いていますので、
使った刀がそうであるというわけではありません。
そこはご了承くださいませね。。
さて、日本刀の全体像はこんな感じ。
.jpeg)
外国のナイフなどには無い
反りのある美しい姿をしています。
今日お話したいのはココ
.jpeg)
日本刀の先の方。
説明しにくいので、
90°回転
ついでに拡大。
2.jpeg) 帽子(ぼうし)と呼ばれる部分です。
帽子(ぼうし)と呼ばれる部分です。
帽子の中には
よく見るとさらに刃文があります。。
2.jpg) この刃文が返っているところ
この刃文が返っているところ
つまり丸くカーブしているところが
小さくて(小丸(こまる)に返る)
さらに
刃の部分=「ふくら」と呼ばれる部分と
.jpg) 平行であれば
平行であれば
.jpg) 肥前刀(九州の方の刀)であるというヒントになるのです。
肥前刀(九州の方の刀)であるというヒントになるのです。
昨日お話した三品(さんぴん)帽子(ぼうし)は
この刃文が少したわんだ感じ。
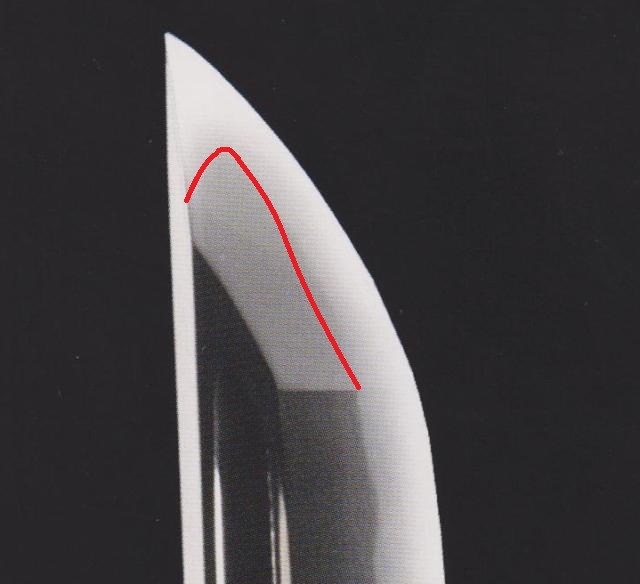 「伊賀守金道(いがのかみきんみち)」などの刀工が
「伊賀守金道(いがのかみきんみち)」などの刀工が
鍛(きた)えた刀の特徴でもあります。。
こんな風に少しずつ
色んな事をおぼえていくのが
日本刀を楽しむコツ。
【緑由】まだまだこれからです。
ちょっとずつでも
学んでいけたら。。
好きなことですもの
頑張らなくっちゃ!
最後まで読んで下さってありがとうございます。
↓こちらもポチっとクリックして下さると、とっても嬉しいです♪
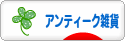
今回、使わせていただいた
『讃州鍛冶』の本。
ご興味がおありなら
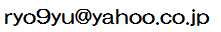
までお問い合わせくださいませ(スパムメール対策のため画像にて表示しています)。
詳しい内容をお知らせいたします。。

![]()






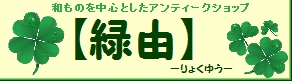















-734x1024.jpg)
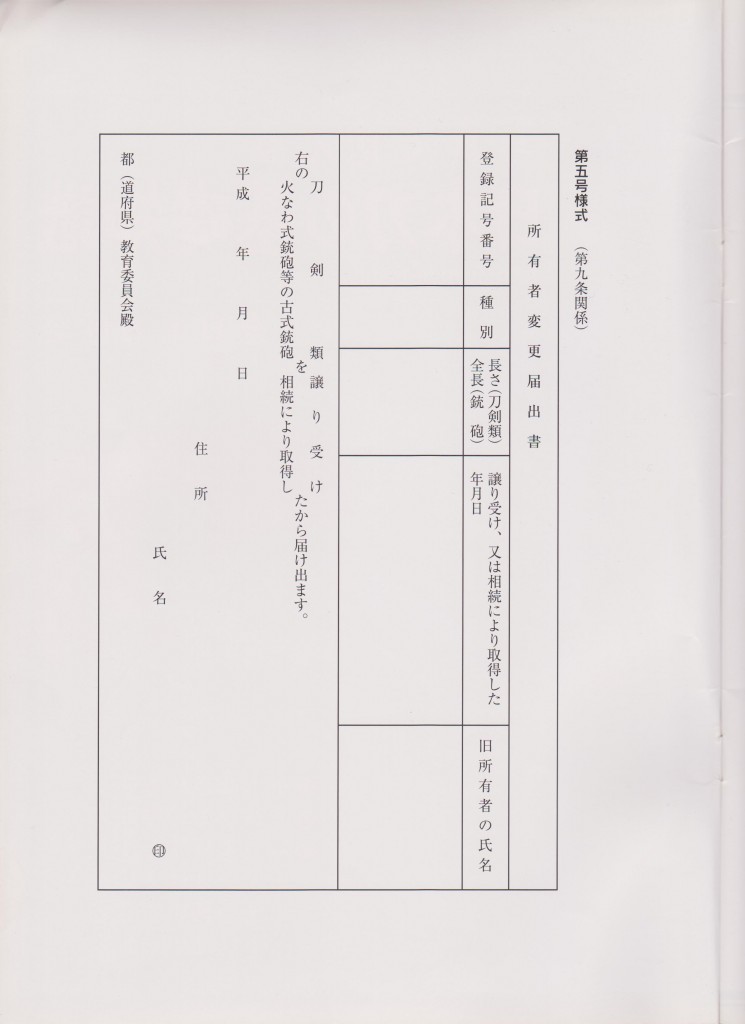
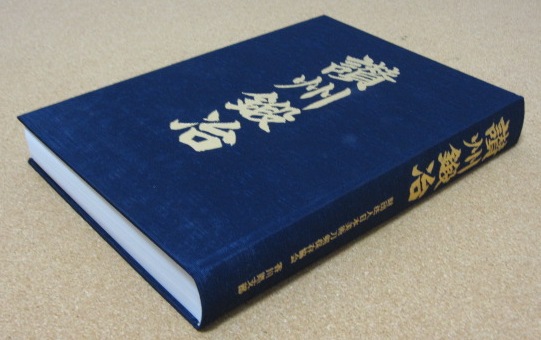
.jpeg)
.jpeg)
2.jpeg)
2.jpg)
.jpg)
.jpg)
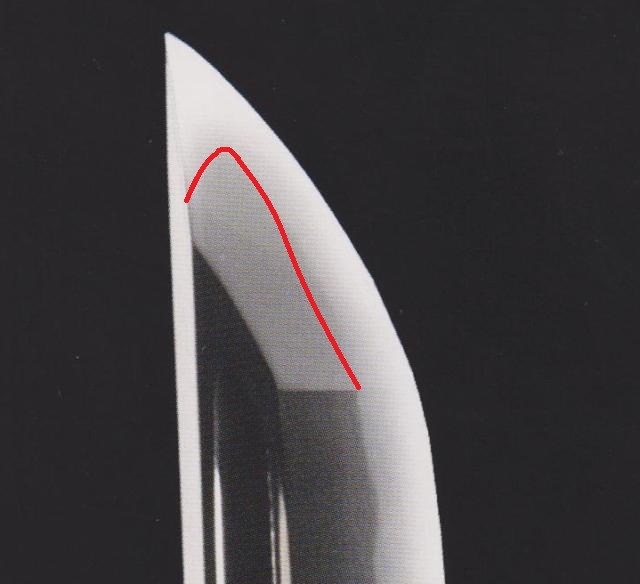

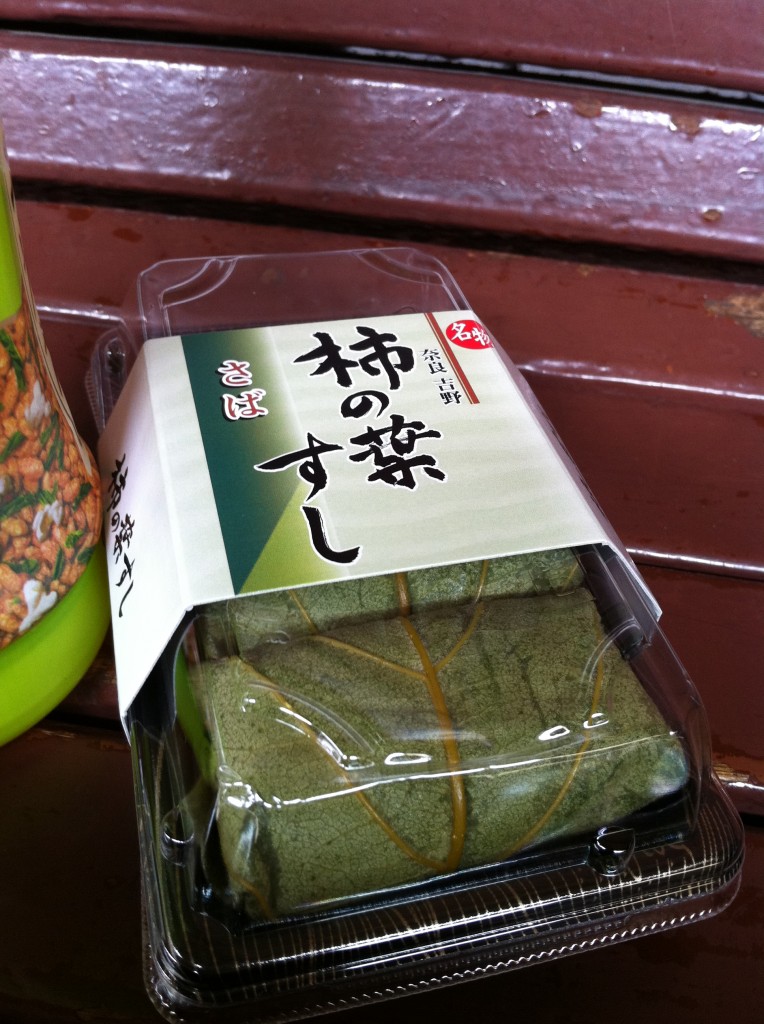












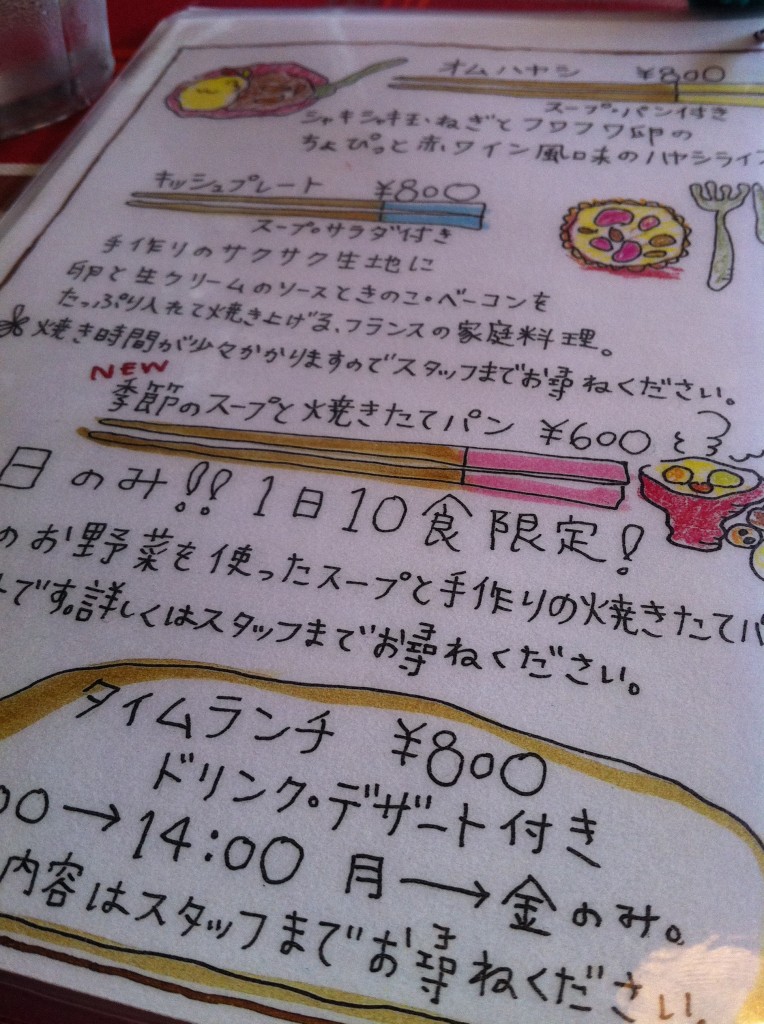
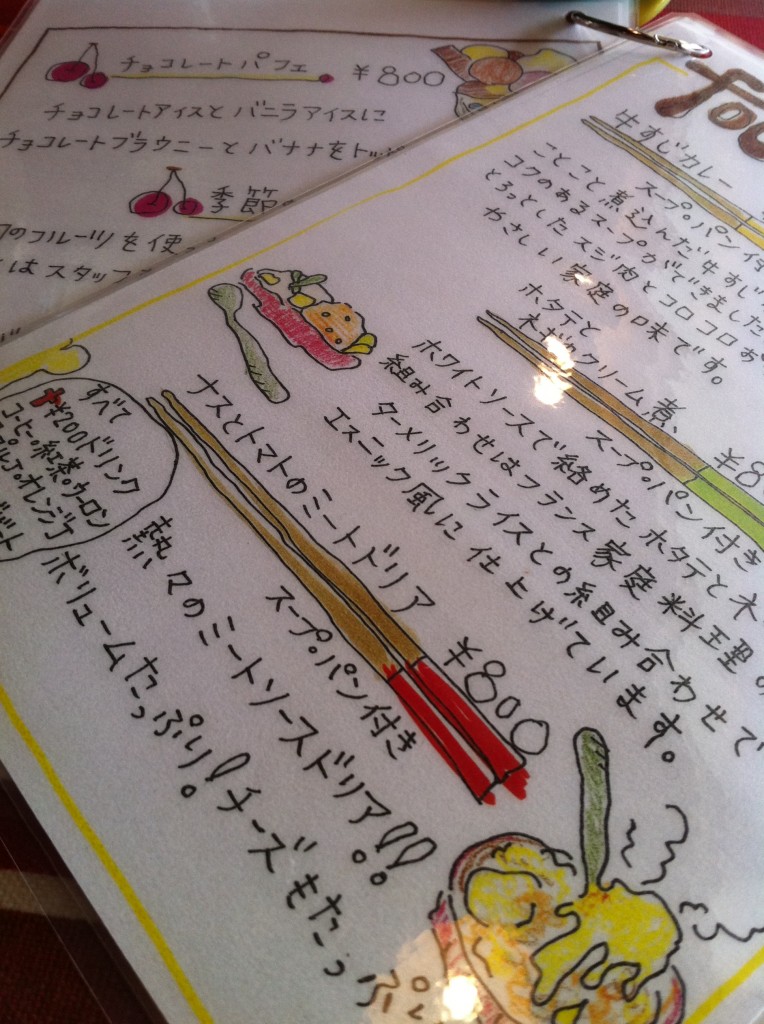
.jpeg)
.jpeg)


