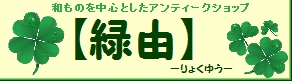ブログランキングにご協力お願いしまーす。
↓クリックして下さるとカウントされてランキングが上がります。。
![]()
おっとっと。
今日は、少し更新が遅れてしまいました。。
今日は、油壺(あぶらつぼ)についてお話しませう。

昔むかし、まだ電気がなかったころの話。
人々は、菜種油をつかって明りをとっていました。
その菜種油を入れて保管しておくのにつかわれていたのが、この油壺(あぶらつぼ)。
実際に使われていた油壺(あぶらつぼ)かどうか見分けるのは、とっても簡単。
口の部分の
匂いを嗅いで下さい(笑)。
油のにおいが微(かす)かにでもしたら、
それは、実際に使われていた油壺(あぶらつぼ)で、時代のあるアンティークだということがわかります。
。。。案外、原始的な手段で古さを見分けるのもアンティーク界ならではですね。。。(笑)。
油壺(あぶらつぼ)は、小さくて色々な種類があるので
専門のコレクターがいらっしゃったりして
人気商品だったりします。
この九谷焼の油壺(あぶらつぼ)も
ぽってりとした胴部分が
手の中にすっぽりと納まって
肌触りも抜群。
ずっと撫(な)でなでしていたいコです。

そうそう、
伊万里や九谷焼で人気なのが

こういう模様(落款?)が入っているとき。

「角福(かくふく)」といいます。
文字通り、四角のなかに「福」が入っているから。
他にも、渦巻きのようにみえるようにデザイン化した「福」、
「渦福(うずふく)」なんかもあります。
油壺(あぶらつぼ)は、現在ではそのままインテリアにしたり
一輪挿しにしたり。
花器として使われることが多いでしょうか。。
現代の生活の中のちょっとしたアンティークとして
とても重宝するコだったりします。。。